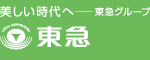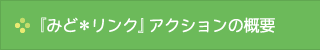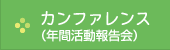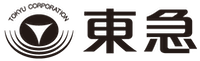活動レポート 2025年05月20日
2025年度『みど*リンク』アクション【スパイスアップ SOZAi循環Lab】
5月20日、横浜市青葉区上谷本町にある畑の一角で、『みど*リンク』アクションが開催されました。支援グループは、第12回(2024年度)の『みど*リンク』アワードに選出された「スパイスアップ SOZAi循環Lab」です。
「SOZAi循環Lab」は、生活者の視点から、身近な素材を楽しみ深く知ることを通して、サステナブルな商品の開発や暮らしの行動変容を目的とした地域共創に取り組む、ネットワーク型のリビングラボです。この取り組みでは、地域の人と人とのつながり、環境、技術を生かし、地域のあちこちに小さな循環を生み出す活動を行っています。
2025年度の活動は、生きづらさを抱える人々との交流を深め、新たなコミュニティー形成に取り組むと同時に、竹や竹炭、竹林を地域で活用する仕組みづくりを進めます。また、青葉台リビングラボの協力の下、横浜市立青葉台中学校科学部と共同で、竹を細かく砕いた「竹チップ」を用いたキノコの栽培にも取り組む予定です。
本日の活動は「竹のワークショップ」です。たき火の炎で竹筒ご飯を炊くほか、竹を削って箸やコップなどのカトラリーを作る竹細工作りも行われました。参加したのは、SOZAi循環Labメンバーと地域住民のみなさん。
火起こしや竹細工作り、調理など、参加者それぞれが主体性を持ちながら分担し、手際よく作業をこなしていきます。

鉈(なた)で竹を細く割き、箸の素材を作ります

先端をナイフで削り、形を整えていきます

節の部分を底にして、のこぎりで竹のコップを作ります

竹筒ご飯を作るために必要なたき火の火起こし
それぞれの作業が一段落したところで、美しい夕日を背景に参加者全員で記念撮影。
その後、見事に完成した竹のコップを手に、全員で乾杯しました。今年度の活動やメンバーの役割について、代表の柏木さんから報告があった後、『みど*リンク』アクション認定証と、『みど*リンク』アワードの表彰状を参加者全員で共有しました。

今年度の活動を報告する代表の柏木さん
参加者の方が「絶景を見せてあげる」と案内してくださった先は、活動場所からすぐ近くの水を張った田んぼ。夕焼け空が鏡のような水田に映る、田植え前の時期にしか見ることのできない幻想的な光景が広がっていました。

水田が夕焼けを映し、とても幻想的
たき火の炎が安定してきたところで、竹筒ご飯の準備をします。竹筒で作った器に米と水を入れ、フタをかぶせて火の上にセット。水分を含んだ若竹の緑色が墨色になるまで、約30分間蒸していきます。今朝刈り取られたばかりの竹で作った器からは、みずみずしさを感じることができます。

竹筒の中に米と水を入れ、たき火の上にセットして、炊飯開始

竹筒ご飯の完成。お米の粒が立っていて、とってもおいしそう!
竹の芳ばしい香りが感じられるご飯は絶品。「竹林工房 遊-Yu-」に併設している和風ダイニング「仁-Jin-」のメンバーによる手料理とともに、竹筒ご飯を参加者全員でいただきました。
初夏の過ごしやすい空の下、おいしいご飯と楽しい会話が至る所で弾み、参加者の皆さんの笑顔があふれるイベントとなりました。

おいしさに思わずこぼれる笑顔
スパイスアップ SOZAi循環Lab 柏木 由美子さんコメント
『みど*リンク』アクションへの応募は今年度で2回目となりました。第12回の『みど*リンク』カンファレンスでは、昨年度の活動がアワードを受賞し、自分たちの活動が評価されたことに喜びを感じています。
竹の裁断や加工には、のこぎりや小刀など数多くの道具を使用します。活動を重ねるにつれて、これらの道具には、さびや刃こぼれが生じメンテナンスが必要となります。いただいたご支援を、これらの道具の維持管理に充てられることに深く感謝しています。
また、ご支援のおかげで、「竹の実験」に必要な備品の調達がより幅広く可能になり、実験内容も多岐にわたるようになりました。実験の幅が広がれば、参加者に提案できる活動の範囲も増えます。
昨年、活動をしていく中で、実験やイベントを体験したいと感じている若い人が多いことがわかりました。その気持ちに応えられるよう、誰もがやりたいことを自由に楽しめる環境作りに力を入れていきたいと考えています。
さらに今年は、生きづらさを抱える人々が、竹を通じて周囲との関わりを広げられるような取り組みにも力を入れていく予定です。竹をツールとしてコミュニティーの広場を作り、誰でも気軽に参加できる雰囲気づくりを目指します。
また、横浜市立青葉台中学校科学部との共同研究プロジェクトとして、「抗菌作用を持つ竹では、キノコは育たない」という一般論を確かめるために、竹チップを用いたキノコ栽培の実験にも果敢に挑んでいきたいと思っています。土壌に返る竹チップでのキノコ栽培が可能となれば、資源の循環に貢献できると考えています。
昨年同様に、竹の魅力を五感で楽しんでいただくための「竹フェス!」なども引き続き開催しながら、地域とのつながりや交流を大きく広げていきたいと考えています。いつでも好きな時に参加できる自由な空気感で、多様な人々で構成されるグループになれたらうれしく思います。